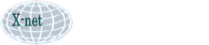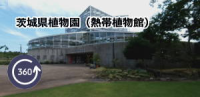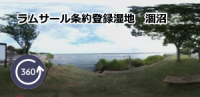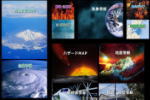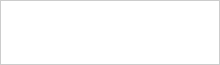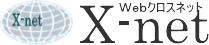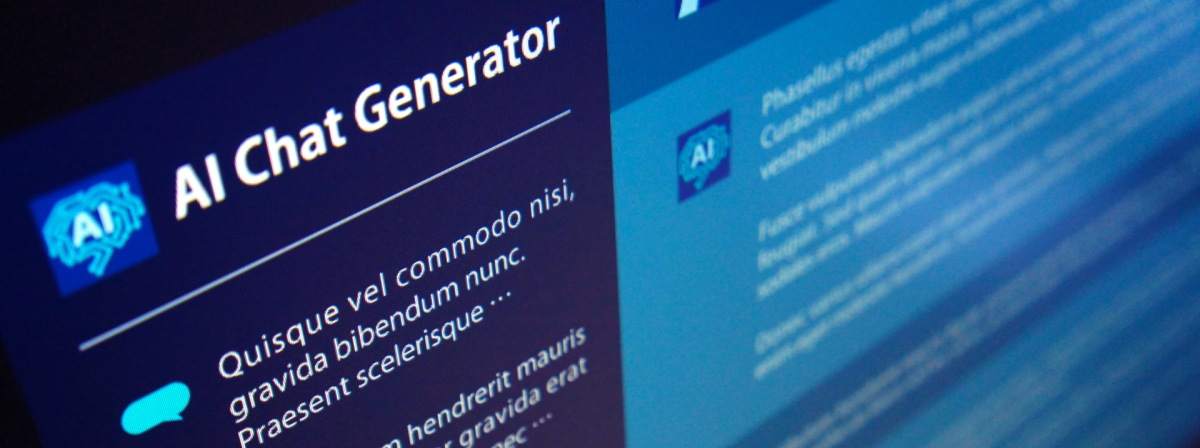
話題の『バイブコーディング』に係る最新動向及び可能性と課題について、AI検索を利用して調べて見ました。
▮ バイブコーディングとは
バイブコーディングは、AIに自然言語で指示を出し、開発をAIに「委ねる」新しいプログラミング手法です。これにより、開発者は詳細なコードを書く作業から解放され、より抽象的なアイデアや設計に集中できます。非エンジニアでもプログラミングに挑戦しやすくなるため、ソフトウェア開発の民主化が進むと期待されています。
▮ 最新動向
バイブコーディングの分野では、LLM(大規模言語モデル)ベースのコード生成ライブラリや、自律型AIエージェントの開発が進んでいます。特に自律型エージェントは、人間が抽象的な目標を与えるだけで、計画立案からコード生成、テスト、エラー修正までの一連のソフトウェア開発サイクルを自律的に実行しようと試みています。これにより、開発プロセスが「生成→検証」の2ステップに簡素化される可能性が指摘されています。
また、企業での導入も加速しており、中にはAIが生成するコードの比率が9割を超える企業も現れています。プログラミング教育の分野でも、バイブコーディングを活用した学習手法が導入され始めており、この新しい潮流が教育や業界全体に大きな変化をもたらしつつあります。
以下に、バイブコーディング完全入門解説ビデオ(配信元:いけともch)をご紹介します。
▮ 可能性と課題
バイブコーディングには次のような可能性があります。
開発速度の向上と効率化:
AIがコードを自動生成するため、開発時間が大幅に短縮されます。これにより、企業の開発プロセスが根本的に変わり、市場投入までのスピードが加速します。
プログラミングの民主化:
専門的なプログラミング言語の知識がなくても、自然言語でAIに指示を出せばコードを生成できるため、プログラミングの敷居が大きく下がります。これにより、多様な人々がアイデアを形にできるようになります。
開発者の役割の変化:
開発者は、コードの実装者から、AIが生成したコードのレビューや検証、そしてより高度な設計やユーザー体験(UX)の創造に注力する「監督者」へと役割が変化していきます。
バイブコーディングには、以下のような課題があります。
| コードの品質と信頼性 | AIが生成したコードには、セキュリティ上の脆弱性やバグが含まれる可能性があります。そのため、人間による厳密なレビューやテストが不可欠です。 |
| 法的な懸念 | AIが学習データに用いたコードの著作権や、生成されたコードの責任の所在など、法的なルールがまだ明確に定まっていません。オープンソースライブラリのライセンス違反リスクも考慮する必要があります。 |
| 過信・依存のリスク | AIの能力を過信し、コードの検証を怠ると、予期せぬ不具合やセキュリティリスクを招く可能性があります。 |
| デバッグと保守の難しさ | AIが生成したコードは、意図を理解しにくく、不具合が発生した場合のデバッグや長期的な保守が難しくなることがあります。 |
▮ 関連情報
●バイブコーディングの可能性と課題 – @IT
●AIエージェント時代に活躍するスキルやノウハウを学ぶ – いけともch